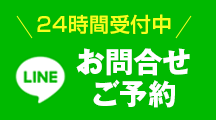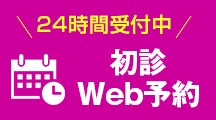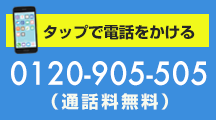- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月

いつ降るかわからない?交通事故予防!降雪前の運転の準備対策
【さいたま市で冬の降雪時の交通事故に備える】
冬になると、「今日は雪は降らないだろう」と思って運転していたところ、突然の降雪や路面凍結により交通事故が発生するケースが増加します。
特にさいたま市周辺では、積雪が少ない分、ドライバーの雪道対策が不十分になりやすいという特徴があります。
今回は、【いつ降るかわからない雪に備えた交通事故予防対策】
【降雪前に必ず行っておきたい運転準備】
について、交通事故治療の予防対策を提唱する花月接骨院からのアドバイスです。

冬はなぜ交通事故が増えるのか?
冬季に交通事故が増える主な理由は以下の通りです。
- 突然の降雪・みぞれによる路面状況の変化
- 朝晩の路面凍結(ブラックアイスバーン)
- 日照時間が短く視界が悪い
- スタッドレスタイヤ未装着、古いスタッドレスタイヤの使用
- 「少しぐらいの雪道なら大丈夫」という油断
特に降雪初日は、運転者が雪道に慣れていないため事故率が急上昇します。

雪前に必ずしておきたい運転準備対策
① スタッドレスタイヤ・チェーンの確認
- スタッドレスタイヤは溝の深さも重要
- チェーンは「持っている」だけでなく装着練習を大事
- 年式の古いスリップサインの出ているスタッドレスタイヤの交換
※さいたま市でも突然の降雪時にチェーン規制がかかることもあります。
② 車間距離は「いつもの2~3倍」を意識
雪道では制動距離が通常の2〜3倍になります。
早めの減速・余裕ある車間距離が事故防止の基本です。
③ 急操作は絶対に避ける
- 急ブレーキ
- 急発進
- 急ハンドル
これらはスリップの原因になります。
すべての操作を【ゆっくり】【ソフトな操作】が鉄則です。
④ フロントガラス・ライトの凍結対策
- 解氷スプレーの常備
- ライト・ウインカーの雪除去
視界不良による追突事故は非常に多く見られます。
降雪時・雪解け後に多い交通事故の特徴
- 低速でも起こる追突事故
- 交差点でのスリップ事故
- 雪解け水によるブラックアイスバーン
「スピードが出ていないから大丈夫」
「雪がやんだから大丈夫」
という油断が事故につながります。

冬の交通事故で特に多いケガとは?
雪道事故では以下の症状が多く見られます。
- むちうち(頚椎捻挫)
- 首・肩・背中の痛み
- 腰痛
- 頭痛・めまい・吐き気
- 数日後に出てくる違和感
事故直後に痛みがなくても、
数日〜1週間後に症状が出るケースが非常に多いのが特徴です。

単なる雪のスリップ事故!「たいした事故じゃない・ケガじゃない」と思っていませんか?
低速事故・追突事故でも、体には大きな衝撃が加わっています。
特にむちうちは、
- 放置すると長期化
- 天候や寒さで悪化
- 後遺症につながる
こともあるため、早期対応が重要です。
降雪時の交通事故対応の注意点
降雪時は、あちらこちらで交通事故が多発します。
なので警察に連絡してもすぐには対応しきれず、場合によっては数時間待つこともあります。
救急搬送が必要のない時は、相手側との必要最低限の情報交換
・免許証の確認
・任意保険の確認
・連絡先の交換確認
・事故状況の証拠写真撮り
を行った後、
周囲の道路状況を確認しながら、必要に応じてさらなる追加の交通事故が起こらないように車両の移動等も警察に連絡して検討しましょう。
その後、降雪による体の冷えなどの体調不良を起こさないように、車両内やすぐに対応できる施設に避難して待つようにしましょう。

交通事故後の治療は接骨院でも可能です
交通事故によるケガは、自賠責保険を使って自己負担0円で施術を受けることができます。
- 整形外科との併用OK
- 通院慰謝料の対象
- 保険会社対応のサポートあり
さいたま市緑区の花月接骨院では、交通事故治療・むちうち治療に力を入れています。
花月接骨院が冬の交通事故患者様に選ばれる理由
- 交通事故治療の専門対応
- 症状に合わせた段階的施術
- 後遺症を防ぐケア
- 保険や手続きの丁寧なサポート
- 地域密着で通いやすい
冬は症状が長引きやすい季節だからこそ、すぐの対応が重要です。

Q&A(雪道事故編)
Q.雪の日の軽い追突でも治療は必要?
A.はい。低速でもむちうちになるケースは多くあります。
Q.数日後に痛みが出た場合も保険は使えますか?
A.問題ありません。交通事故との因果関係が認められます。しかし早めに受診するようにしましょう。※2週間以上経過後は、対応が困難になる場合があります。
Q.雪道事故後はすぐ受診すべき?
A.痛みがなくても、早めの受診が痛みの悪化、後遺症予防につながります。

まとめ|雪は「降る前」の準備が事故を防ぐ
雪は予測できても、いつ・どこで・どの程度降るかは分かりません。
だからこそ、天気予報の情報をしっかり確認して
- 事前の準備(情報収集)
- 慎重な運転(車の運転をしない事も検討)
- 事故後の早期対応(痛みが無くても後から出てくる痛みの対策)
がとても大切です。
もし雪道での事故や違和感があれば、さいたま市緑区の花月接骨院までご相談ください。
早めの対応が、後遺症の予防につながり、将来の体の健康状態を守ります。
【降雪の運転の準備をしっかりしたのに、雪が降らなかった】
それでもしっかりと予防対策の練習として、毎回準備をしましょうね。

交通事故のむちうちとは?なぜ年末年始に悪化しやすいのか
むちうちとは、交通事故の衝撃によって首がムチのようにしなり、筋肉・靭帯・関節・神経にダメージを受ける状態です。
特に年末年始は、以下の理由で症状が強く出やすくなります。
- 寒さで首・肩の筋肉が硬くなる
- 事故後に十分なケアを受けられない
- 病院が休診で受診が遅れる
- 保険会社の連絡が遅れる
- 長時間の運転や帰省による首への負担
その結果、受診が遅れ、年明けに「首が回らない」「頭痛が続く」「手がしびれる」といった症状で来院される方が増えます。

むちうちは「事故直後に痛くない」が一番危険
交通事故直後に痛みが少ない理由は、アドレナリンによって痛みを感じにくくなっているためです。
むちうちの典型的な経過は以下です。
- 事故当日:ほぼ痛みなし
- 翌日〜3日後:首の違和感・重さ
- 数日後:可動域制限・頭痛・肩こり
- 放置:慢性痛・天候で悪化する後遺症
年末年始に多いのが、「休み明けまで我慢 → 症状が固定化」というケースです。
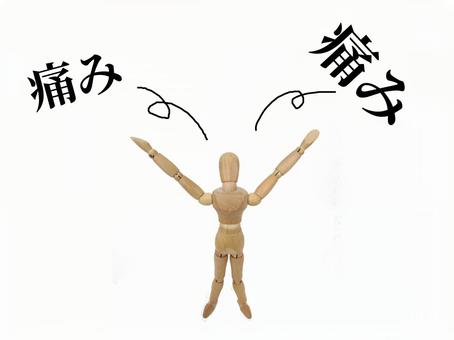
年末年始に交通事故むちうちでやるべき行動
① 首に違和感があればすぐ相談
「この程度なら大丈夫」は禁物です。
むちうちは早期の評価と施術が回復を左右します。
② 病院が休みでも“むちうち専門院”を選ぶ
整形外科が休診している年末年始でも、
むちうち治療に特化した接骨院で初期対応が可能です。
後日、整形外科との併用も問題ありません。
③ 自賠責保険は年末年始でも使える
交通事故によるむちうちは、
自賠責保険適用で窓口負担0円です。
「休みだから手続きできない」ということはありません。

さいたま市緑区で“むちうち治療専門院”を選ぶ基準
むちうちは、一般的な肩こり治療とはまったく違います。
以下の条件を満たす院を選ぶことが重要です。
- 交通事故・むちうち施術の実績が豊富
- 首の可動域・神経症状を細かく検査できる
- 炎症期・回復期を分けた施術計画がある
- 整形外科との併用を前提にしている
- 保険会社対応の知識がある
むちうちは「専門院でなければ見抜けない微細な異常」が多い症状です。

花月接骨院が“交通事故むちうち治療専門院”として選ばれる理由
さいたま市緑区原山にある花月接骨院では、交通事故によるむちうち治療やケガを専門的に行っています。
✔ むちうち特化の検査と評価
首の動き・筋緊張・神経反射を細かく確認。
✔ 状態に合わせた段階的施術
- 炎症期:負担をかけない施術
- 回復期:可動域改善
- 安定期:再発防止ケア
✔ 整形外科との併用OK
診断書・検査結果を活かした施術が可能です。
✔ 自賠責保険対応(0円)
通院・慰謝料に関する不安も丁寧に説明します。
Q&A
むちうち治療・年末年始編
- 年末年始でもむちうち治療は受けられますか?
A. はい。病院が休診でも、むちうち専門院で初期対応が可能です。 - 痛みが軽くても通院した方がいい?
A. はい。むちうちは遅れて悪化するため、早期受診が重要です。 - 首の痛みだけでも自賠責保険は使える?
A. 使えます。むちうちは自賠責保険の代表的な対象症状です。 - 年明けから通院しても遅くない?
A. 遅くなるほど回復に時間がかかるため、早めの相談をおすすめします。

まとめ
年末年始のむちうちは“早めの対応”がすべて
交通事故によるむちうちは、年末年始の対応の遅れで「後遺症」になることもあります。
- 首の違和感
- 動かしにくさ
- 頭痛・吐き気
これらがある方は、我慢せず早めにご相談ください。
さいたま市緑区で交通事故むちうち治療専門院をお探しの方は、花月接骨院がしっかりサポートしますのでお気軽にお問い合わせください。

【交通事故のケガ診断書の「全治の期間」とは?】
交通事故後に言われる「全治○週間」とは?
交通事故後、整形外科などで発行される診断書には「全治2週間」「全治1か月」などの記載があります。
この「全治の期間」とは、
ケガが医学的に回復するまでの目安期間であり、症状固定や完治を保証する期間ではない
という点が非常に重要です。
多くの方が「全治2週間=2週間で完全に治る」と誤解しやすい部分でもあります。
なので、交通事故でケガをされた被害者様が、【2週間しか通院できないの?】と誤解しやすい話となります。
あくまでも、交通事故での診断書は、人身事故扱いにすると、加害者にどの程度の行政処分をする目安の為の期間となります。
つまり警察提出用であり、実際に感知するために通院する期間とはほぼ関係ないこととなります。

全治期間はどのように決められる?
診断書の全治期間は、主に以下をもとに判断されます。
- 受傷部位(首・腰・肩・膝など)
- ケガの種類(打撲・捻挫・挫傷・むち打ち)
- 初診時の痛み・可動域制限
- 画像所見(レントゲン・MRIなど)
- 医学的な一般的回復目安
つまり、
**事故直後の状態を基準にした「初期予測」**であり、その後の経過は反映されていないことがほとんどです。

全治期間と実際の回復期間は違う?
多くの場合で違います。
特に交通事故では、
- 数日後から痛みが強くなる
- 炎症が長引く
- 深部組織(筋膜・靱帯)の回復が遅れる
といったケースが非常に多く、全治期間を過ぎても症状が残ることは珍しくありません。

全治期間が短いと不利になる?
結論から言うと、不利になる可能性があります。
- 治療期間の目安
- 保険会社の対応判断
- 通院の正当性
などに影響することがあるためです。
ただし、
・症状が残っていれば治療は継続可能
・再診や診断書の再発行で期間変更も可能
です。
我慢して通院をやめる必要はありません。

花月接骨院が考える「全治期間」と交通事故治療
■ 全治期間より「症状と回復過程」を重視
花月接骨院では、
診断書の全治期間よりも、
- 現在の痛みの強さ
- 動かしたときの違和感
- 日常生活への影響
- 深層筋・筋膜・関節の状態
を重視して治療を行います。

■ 事故特有のケガは回復に個人差が大きい
交通事故の打撲・捻挫・挫傷・むち打ちは、
- 表面の痛みが軽くても
- 深部にダメージが残っている
ことが多く、
回復スピードには大きな個人差があります。
花月接骨院では、
- 視診・触診
- 可動域検査
- 徒手検査
- ハイボルト検査
などを用いて、現在の回復段階を正確に把握します。
■ 状態に応じた治療法の使い分け
回復段階に応じて、
- ハイボルト治療(原因部位特定・鎮痛)
- 微弱電流治療(組織修復)
- 遠赤外線レーザー治療
- 遠赤外線振動波治療
- アイシング(急性期)
- ウォーターベッド療法
- 酸素カプセル(疲労回復・修復促進)
を必要な分だけ選択します。
■ 日常生活指導も治療の一部
全治期間内・期間後に関わらず、
- 仕事・家事・運転時の注意点
- 悪化しやすい動作
- 睡眠姿勢の工夫
などの日常生活指導アドバイスも行い、
回復を妨げる要因を減らします。

■ 治療終了の判断は「痛みがなくなった時」ではない
花月接骨院では、
- 痛みが軽減した
- 日常生活ができる
だけで治療を終えることは推奨していません。
深部組織まで回復しているか
再発・後遺症リスクが残っていないか
を確認することが、将来起こるかもしれない後遺症リスクを軽減させます。

■ 診断書・保険・通院の不安もご相談ください
- 診断書の全治期間について不安がある
- 保険会社とのやり取りが心配
- 病院と接骨院の併用通院について知りたい
こうしたお悩みも、交通事故対応に慣れた花月接骨院がサポートします
お気軽にさいたま市の花月接骨院までご来院ください

【12月〜年末年始は交通事故が増える時期】
12月に入り、今日は浦和では年末恒例の十二日まち(大歳の市)。新年に向けてさいたま市でも年末の慌ただしさが増えてきました。
でも注意しなくてはならないのが、実はこの時期、全国的に【交通事故が特に増える季節】でもあります。
花月接骨院(さいたま市緑区原山)にも、例年、年末年始にかけて むちうちや腰痛などの交通事故によるケガで来院される方が急増します。
そこで今回は、
【なぜ12月・年末年始は交通事故が多いのか?】
【交通事故に巻き込まれたら最初にやるべきこと】
【交通事故のケガ・むちうちを悪化させない対処】
をまとめた、花月接骨院のあるさいたま市在中の方に向けた“実用性を重視した記事”です。
交通事故後の体の痛みは、早期に適切に対処できれば早期快復、後遺症を大幅に防げます。特にむちうち・腰痛・背部痛などは、事故直後だけでなく翌日から痛みが強くなるケースが多く、適切な初期対応と専門施術が非常に重要です。
ぜひ最後までご覧ください。

なぜ12月は交通事故が増えるのか?(さいたま市の特徴)
- 日没が早く、「夕暮れ事故」が急増する
12月のさいたま市の日没は16時半ごろとなります。
仕事・買い物・塾の送迎で車が増える「夕方の時間」と重なり、歩行者や自転車の発見が遅れやすいため事故が増えます。
特に、
花月接骨院周囲のメイン道路(産業道路・第二産業道路・浦和越谷街道・新浦和越谷街道・国道122号)などでも交通量は増加!原山/中尾/大谷口/東浦和では交通渋滞も多発し始めます。そのためこの地域は、住宅街が多く細い裏道で、車・歩行者・自転車との接触事故が増える傾向があります。
- 路面の温度低下で“スリップ”が起きやすい
雪が少ないさいたま市でも、「路面が冷えた早朝・夜間のスリップ」 は毎年多く発生します。橋の上・小さなトンネル出入り口・陽が当たりにくい道路は、特に摩擦が弱くなるため、急ブレーキでスリップ事故が起こりやすくなります。
- 年末の慌ただしさ・疲労運転・自転車の飲酒運転
12月は、残業、忘年会、長距離運転、年末の買い出し等で交通量そのものが増加します。さらに、忙しさからくる注意力の低下・判断の遅れも事故増加の大きな原因となります。また、昨年からの自転車の飲酒運転NG!皆様覚えていますか?このような飲酒自転車運転も交通事故増加の要因になっています。
事故後は痛みがなくても受診が必要な理由
交通事故直後は、痛みが出なくても安心できません。
これは アドレナリンの影響で痛みを感じにくくなる ためです。
【むちうち】【腰痛】【打撲】【捻挫】【筋損傷】は、事故直後はあまり痛くなくても、翌日〜3日後に強くなるケースが多数あります。
特にむちうち症状は
1日後、2日後、最長1週間後に出てくることも珍しくありません。
放置すると、頭痛/吐き気/めまい/倦怠感/首の痛み/首の可動域制限/天候で痛む後遺症などにつながる可能性があります。
花月接骨院では、事故直後の受診段階から【まだ感じていない損傷】にも油断せず治療を進めていきます。

交通事故直後にやるべきこと【保存版】
①警察に連絡する
軽微な物損事故・人身事故でも、警察に連絡して事故の発生を届けること必須です。
この届けをしないと、交通事故のケガと認めてもらえず、自賠責保険での治療や任意保険の物損修理の対象にならない可能性が大いにあります。
②保険会社へ連絡する
治療費の窓口負担0円で通院できます。
※受診後でも問題ありませんが、
③必ず病院で診察・診断を受ける(診断書は人身事故扱いの場合に必要となります)
また、接骨院で治療を受けるためにも、医師の診察は治療部位の確認の為にも大切となります。
よく聞かれるお問合せでは、病院?接骨院?どちらを先に受診した方がよいのか?とありますが、基本的には受診順番はどちらが先でも問題ありません。特に年末年始は、整形外科の医療機関が休診、保険会社の人身事故担当が決まらないとなることがあります。
痛みがある場合は、保険会社への連絡よりも先に来院してもOKです。後から連絡しても大きな問題はありません。
また当院では、痛みの場所の確認と治療を行い、休み明けに連携医療機関をご紹介し受診できるようにしています。
大切なこととしては、できるだけ早く治療を開始すること
・初期の治療が遅れると治り(痛みの改善率)が悪くなる傾向があります。
・病院と接骨院は併用がベスト
病院=診断・画像・定期検査
接骨院=治療・リハビリケア治療
双方の長所を活かすことで後遺症を残すリスクを低下させ回復治療を進めていくことができます。
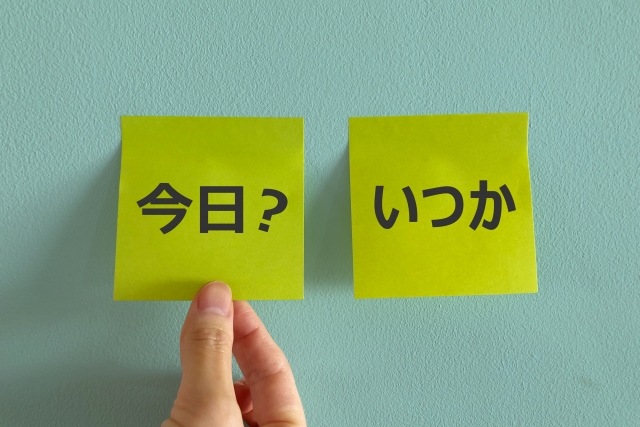
むちうちを悪化させないための初期対応
・首を極端に動かさない
・炎症を抑える、安静姿勢を保つ
・早めに専門院(医療機関・接骨院)へ相談する
・痛みを“我慢して生活しない”
花月接骨院では、
炎症期→回復期→機能改善期 の3段階に分けて、
状態に合わせた施術を行います。

交通事故治療は「どこで治療を受けるか」で回復スピードが大きく変わる?
①事故施術の経験が豊富か
むちうち・腰痛・神経症状など、事故特有の状態を熟知していることが必須。
②保険会社とのやり取りに詳しいか
通院頻度・治療期間の説明ができる院は安心です。
③整形外科との併用サポートがあるか
診断書・紹介状の連携ができる院はトラブルが少ないです。
- 夜間や急患対応が可能か
仕事帰りに通いやすいか急な対応ができるかどうかは非常に重要です。
- 症状説明が丁寧か
来院前のTELして、施術内容・経過予測をわかりやすく説明してくれる院かどうかの確認。
通院する接骨院選びで回復スピードも変わります。
上記を参考にして通院先を選ぶようにしてみてください。

花月接骨院が選ばれる理由(さいたま市内でも特に交通事故治療におすすめな理由)
・国家資格者による検査と施術
・むちうち専門施術
・ショックマスターを始め様々な治療機器完備
・羽田野式ハイボルト療法が受診できる
・病院との併用OK(連携医療先紹介可能)
・自賠責保険サポートがしっかりできる
・後遺症を残さない施術計画
・緑区原山で通いやすい立地(バス停近く・駐車場・駐輪場完備)

まとめと2025年末2026年始のお知らせ
2025年末は12月31日午前中まで診療
2026年始は1月5日より通常診療
年末年始の万が一交通事故に遭ってケガをした場合のご相談は、HPラインから随時対応します。
12月・年末年始の交通事故は“早期対応”が最重要
12月〜1月は、さいたま市でも交通事故が最も増える季節です。
保険会社の治療担当連絡の遅れ・医療機関お休みの時は、接骨院で治療開始しても大丈夫です。少しでも違和感がある場合は早めに花月接骨院ご相談ください。

交通事故治療気になるQ&A
Q1.交通事故の痛みが翌日から強くなるのはなぜ?(むちうち・腰痛)
A1.交通事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくく、数時間〜翌日に炎症が進むことで症状が強く出るためです。むちうち・腰痛・背中の張りなど【遅れて出現して悪化する】のが典型的です。
当院の対応
・初期炎症の抑制
・首・腰の深部まで考えた痛みの評価
・事故特化の施術で回復を早める
Q2. 保険会社への連絡は治療より先?後?
A2.ケガの痛みがある場合は、先に医療機関(接骨院・整形外科)へ行って問題ありません。その後に保険会社へ連絡しても補償に影響しません。
当院のポイント
・来院後すぐに保険会社への連絡方法をアドバイス
・必要に応じて医療機関へ紹介状作成も可
Q3. 年末年始でも交通事故治療は受けられますか?
A3.年末年始は整形外科の休診が増えるため、接骨院での受診が特に重要です。
当院は可能な限り「年末前後の急患受付」に対応しています。
Q4. 交通事故の「後遺症」が残らないために最も重要なことは?
A4.最初の2~4週間に「炎症・可動域・姿勢」の3点を正しく整えることです。
この期間のケアが最終的な回復を大きく左右します。
当院の施術例
・ハイボルト治療
・微弱電療治療
・頚椎・骨盤バランス調整
・ショックマスター併用(必要時)
など
Q5. 病院と接骨院のどちらに行くべき?両方通える?
A5.結論:両方通うのが最もベストです(併用OK)。
病院=診断・画像・定期検査
接骨院=治療・リハビリケア治療
当院のサポート
・併用治療の流れを説明
・整形外科への紹介も可能
Q6. 交通事故の治療費は本当に0円ですか?
A6.はい。自賠責保険が適用されるため、
窓口負担は 0円 です。
休業補償・通院慰謝料も対象になります。
Q7. 保険会社から“そろそろ治療を終了しましょう”と言われた場合は?
A7.主治医と接骨院の評価が優先されるため、痛みが残っているなら継続可能です。
保険会社の提案に従う必要はありません。自分の状態に合わせてしっかり保険会社担当と話しましょう!
当院の対応
・症状の経過資料を作成
・継続理由を保険会社に説明アドバイス
Q8. 夜に痛みが強くなる理由は?
A8.気温低下、体の冷え、日中の負荷の蓄積により、炎症が悪化しやすいからです。冬季は特に増えます。
当院の冬対策
・温熱+深部筋ケアアドバイス
・首・腰の冷え対策指導
Q9. 交通事故の痛みが改善しづらいタイプは?
A9.下記のような方は“慢性化しやすい”傾向があります:
・冷え性の方
・デスクワークが多い方
・姿勢が悪い方
・もともと肩こり・腰痛がある方
・屋内野外で中腰作業の多い方
・ストレスが多い方
当院では上記のような改善しにくい方にも改善させる治療方法で、なおかつ再発しにくい体づくりを提案してます。
Q&Aまとめ
さいたま市緑区で交通事故に遭ったら、まずはご相談ください
特に年末年始の交通事故の痛みは【初期対応】で結果が大きく変わります。
むちうち・腰痛・背中の張りは放置すると慢性化しやすい症状です。
さいたま市緑区で交通事故に遭い、
・どこへ行けばいいか分からない
・翌日から痛みが強くなってきた
・保険会社との連絡が不安
・年末年始で病院が休み
という方は、お気軽に当院へご相談ください。
地域密着院として、痛みの改善から手続きのサポートまでトータルで対応いたします。

交通事故治療とは?多くの交通事故の患者様が当院へご来院される理由は?Q&A
Q.交通事故治療とは?
A.交通事故治療とは、事故の衝撃によって損傷した筋肉・靭帯・関節・神経の機能を回復、痛みを軽減させ、後遺症を残さずに日常生活へ復帰するための専門性の高い施術を行うのことをいいます。
Q.追突事故の代表的なケガとされるむちうちの症状?
A.首・肩の痛み/腰痛/背部痛/手足のしびれ/頭痛・めまい・吐き気等。
事故直後は痛みが出ないことも多く、正確な検査と適切な施術が後遺症ゼロの鍵になります。
Q.なぜ交通事故直後ではなくむちうちの痛みが遅れて出るのか?
A.事故直後は、体が興奮状態になり痛みを感じにくくなるためです。
むちうち・筋損傷は1〜3日後に悪化することが多く、初期対応が遅れるほど回復が長引きます。
花月接骨院では、痛みが出る前から組織の損傷を見つける検査を行い、悪化を防ぎます。
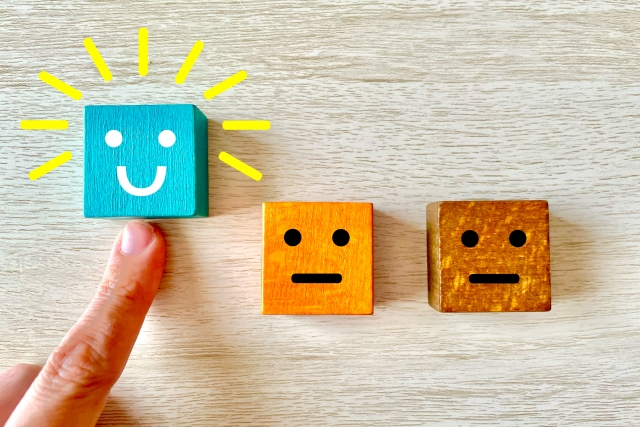
花月接骨院が交通事故治療で選ばれる理由は?
Q.花月接骨院が交通事故治療で選ばれる理由は?
A.
① 国家資格者による専門施術
検査・可動域検査・神経学検査・筋緊張・姿勢分析・自事故状況問診等を行い、症状の原因を正確に特定します。
② むちうち専門施術に対応
深部筋アプローチ・関節調整・筋膜骨膜リリース・電気療法にて、炎症期の軽刺激ケア状態に合わせて安全な施術を行います。
③事故の影響による筋や腱の痛みの軽減に効果的な治療機器
高電圧治療・ショックマスター(圧力衝撃波)・微弱電気治療など様々な専門の高い治療機器の設備を完備しています。
④ 自賠責保険の手続きサポートに精通
通院手順から書類の説明、保険会社対応のアドバイス、法律問題は連携弁護士に無料相談ができますので、はじめての交通事故で安心してご通院できます。
⑤ 病院との併用が可能
医療機関と連携しながら当院で施術できます。(併用は自賠責保険で認められていますのでご通院先の医師に併用加療の希望をご確認ください。なお許可が下りない場合はご相談ください。)
⑥ 後遺症予防に特化した施術計画
痛みの軽減だけでなく、可動域・筋バランス・生活動作の改善、日常生活復帰後までまで一貫してサポートします。

自賠責保険について(治療料金について)
Q.自賠責保険について(治療料金について)
A.交通事故の治療費は、自賠責保険により 窓口負担0円 で受けられます。
自賠責保険適用の範囲
・施術費
・交通費
・休業補償
・1日4,300円の慰謝料
など手続きの流れも当院で詳しくご案内できます。
Q.交通事故治療の流れ
① 来院・問診
事故状況・痛みの出方を丁寧に伺います。
② 検査
むちうち・筋損傷・関節のズレ・痛みの原因を詳細チェックします。
③ 説明
症状の原因・施術計画(来院計画)をわかりやすくご説明します。
④ 施術
第一段階(急性期)-炎症期は負担の少ない施術。
第二段階(回復期)-回復期は根本改善に移行。
第三段階(社会復帰期)-社会復帰期は、日常生活動作を行いながらの施術に移行。
第一段階から第三段階まで、今後の通院計画の必要な来院頻度・自宅ケア等を指導していきます
Q.よくある症状と施術
A.むちうち(頚椎捻挫・外傷性頸部症候群)
・首の筋肉・靱帯の損傷
頭痛・めまい・しびれにもつながるため専門施術が必須。
・首、肩の強い痛み
深部筋の損傷が隠れている場合が多い。
電気施術・手技で改善。
・腰痛・背部痛
衝撃で関節がズレ、筋緊張が起こる状態。
筋膜リリースと姿勢調整が有効。
・しびれ
神経圧迫や炎症が原因。
可動域改善と神経周囲のケアで軽減。

さいたま市緑区で交通事故治療に強い接骨院を選ぶポイント
Q.さいたま市緑区で交通事故治療に強い接骨院を選ぶポイント
A.
・交通事故治療の経験実績が高い
・むちうち専門施術がある
・病院との併用が可能
・保険サポートが丁寧
・専門設備がある
・通いやすい立地(駐車場・駐輪場・公共機関利用・生活道路沿い)
・交通事故専門弁護士との連携
なお、花月接骨院は、これらの条件をすべて満たしています。
Q.対応エリア
A.井沼方・大崎・大牧・大間木・大谷口・上野田・北原・玄蕃新田・道祖土・芝原・下野田・下山口新田・新宿・太田窪・大道・大門・代山・高畑・寺山・中尾・中野田・南部領辻・蓮見新田・原山・馬場・東浦和・東大門・松木・間宮・三浦・見沼・三室・宮後・宮本・山﨑・浦和美園のさいたま市緑区全域・さいたま市浦和区・さいたま市南区・さいたま市見沼区・川口市
の上記地域より多くの患者様にご来院いただいています。もちろんそのほかの地域の方でも対応できますのでお気軽にご来院ください

まとめ
・後遺症を残さないために、早期対応が最重要
・交通事故は、痛みが軽くても必ず早めの検査・施術が必要です。
後遺症を残さず元の生活に戻るために、花月接骨院は専門性の高い施術と丁寧な対応で交通事故被害者様を全力でサポートし支えることが理念です。
お気軽にご相談ください。
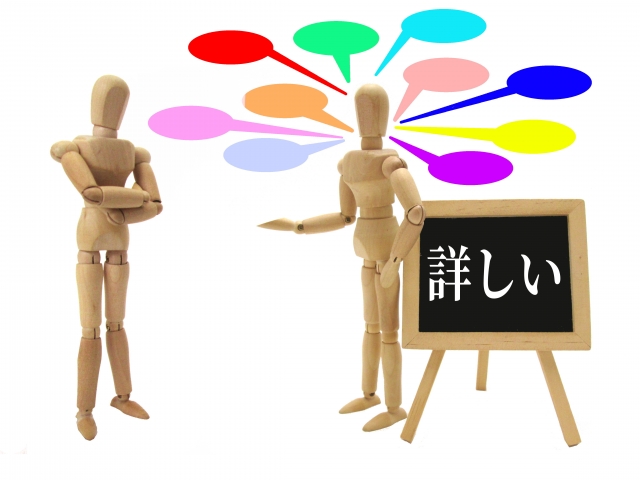
さいたま市緑区で交通事故治療に強い接骨院の選び方|むちうち改善・保険対応に詳しい院を見極めるポイントと当院の強み【保存版】
交通事故に遭った直後は、
「むちうちが心配」
「どこの接骨院へ行けばいい?」
「保険会社とのやり取りが不安…」
など、分からないことばかりです。
特にさいたま市の中心浦和区を始め、ちょっと郊外のさいたま市緑区・南区・見沼区は、交通量が多く、追突事故や交差点事故等が多く発生しており、交通事故治療のご相談やご来院がコロナ後にまた増加し始めています。
そして今の冬の季節は、朝日がまぶしく、また夕暮れを早くなり運転がしづらい時期でもあります。
今回は 【さいたま市(特にさいたま市緑区)で、交通事故治療に強い接骨院を選ぶためのポイント】 を、交通事故治療に精通している専門家の視点でわかりやすく解説します。
さらに、当院がなぜ交通事故治療に強い接骨院か?その強い基準を 花月接骨院(さいたま市緑区原山)がすべて満たしている理由を詳しくご紹介します。

【目次】
1.交通事故治療に強い接骨院を選ぶポイント5つ
2.さいたま市緑区で増えている交通事故の特徴
3.当院(花月接骨院)が交通事故治療に強い理由
4.病院と接骨院は併用できる?
5.事故後によくあるQ&A
6.まとめ:後遺症を防ぐなら「早期治療」が最重要
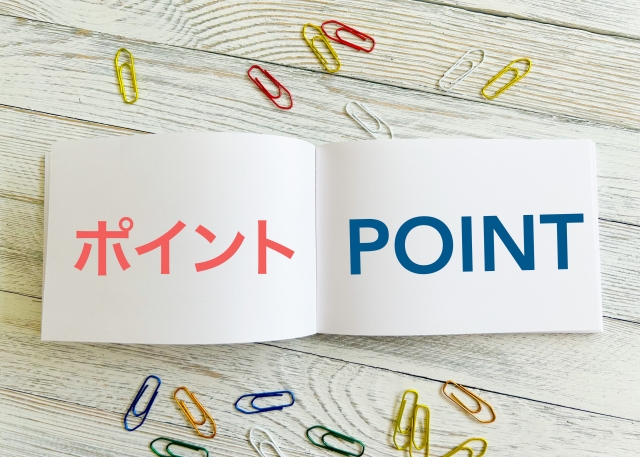
1.交通事故治療に強い接骨院を選ぶ5つのポイント
① 交通事故施術の実績と治療機器設備が豊富か(むちうち・交通事故治療の専門知識があるか)?
交通事故では むちうち・腰痛・肩の痛み・頭痛・手足のしびれ など、レントゲンでは異常が出ない症状が多く見られます。
実績と症例数と院内設備が豊富な院なら、
・むちうちのパターンを熟知
・患者ごとの症状に合わせて施術を調整
・悪化しやすい動作や生活指導も明確
・改善スピード
・治療方針と内容(治療機器)
・遺症リスクを軽減させる指導
ゆえに、実績と治療機器設備は非常に重要です。
② 自賠責保険・保険会社対応に詳しいか?
交通事故治療は、施術だけでなく 保険の知識 も必須です。
・交通事故治療の流れ
・保険会社への伝え方
・病院との併用及び医療連携
・必要書類・手続き(一括請求対応・被害者請求対応・加害者請求対応・労災対応)
・慰謝料や休業補償説明や相談
つまり、これらをしっかりと熟知してサポートできる接骨院は、患者様の負担を大幅に軽減することが可能です。
③ 本当に根本治療にこだわった施術ができるか?
交通事故の痛みは「筋肉」「関節」「自律神経」に影響が出ます。
単なる患部に電気治療だけでは不十分なことも多いため、下記のような施術を症状に合わせた施術が理想です:
・手技療法
・関節調整
・自律神経調整
・姿勢・動作の改善
・生活指導
・再発予防のアプローチ
など、「一時的に楽になるだけ」の施術ではなく、後遺症を残さない治療が重要です。
④ 状態説明と治療計画が丁寧か?
事故後は不安が大きいため、患者様が不安に感じていることを安心する説明してくれる院が信頼できます。
・現在の症状の状態説明※なぜ今の痛みが出現しているのか?
・これからの症状軽減時期の見通し説明
・通院頻度説明※治療計画とリハビリ計画
・回復の見通し※回復を妨げる予防と対策指導
このように、説明が丁寧な接骨院は、治療の質も高い傾向があります。
⑤ 病院(整形外科)との併用・転院に対応しているか?
交通事故は 病院+接骨院の併用が可能です。
病院:診断書、薬、画像検査
接骨院:むちうち改善、可動域改善、リハビリ
とても医療連携は交通事故治療に大切なことで、スムーズに病院の紹介案内、医療連携がしっかりできる接骨院が安心です。

3.さいたま市(さいたま市緑区)で増えている交通事故の特徴
さいたま市緑区は、幹線道路・生活道路・住宅街が混在し交通量が多い地域です。
特に事故が起きやすいのは
- 朝夕の通勤時間帯
- 商業施設路地周辺
- 生活道路の交差点※信号機のない
- 夕暮れ時(視認性が落ちる時間帯)
- 車線変更時や交差点
- 横断中
これらの環境要因から、むちうち・腰痛・打撲で当院にご来院される方が増えています。
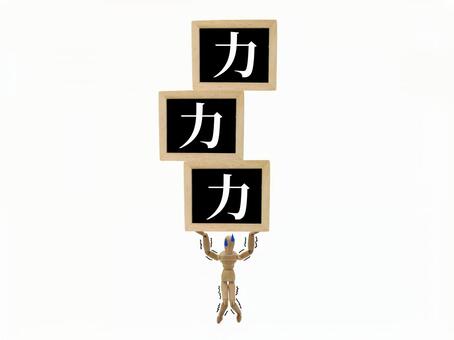
3.当院(花月接骨院)は交通事故治療に強い接骨院です
当院では先ほどの交通事故に強いといえる接骨院の基準をすべて満たしています。
① 交通事故施術の豊富な実績
むちうち・腰痛・肩の痛み・頭痛など、
多くの症状に対応してきた経験と専門知識があります。
炎症期 → 回復期 → 再発予防期
と、症状の変化に合わせて施術を行います。
② 自賠責保険の手続きサポートが徹底
不安を丸ごとサポート
・保険会社とのやり取り
・交通事故治療の手続き
・書類の説明
・併院・転院の相談
・休業補償・慰謝料のしくみ
・弁護士紹介
・医療機関紹介
「初めてで何もわからない…」という方でも安心です。
③ 根本改善をおこなう当院の安心安全な施術
当院が大切にしているポイント
・筋肉と関節の両方にアプローチ
・姿勢や動作のクセを改善
・多種多様な電気治療+手技+調整で回復を早める
・後遺症予防を重視
短期的な改善だけでなく【事故前の生活に戻る】だけでなく【今まで以上に健康に!】を重視しています。
④ 丁寧な説明カウンセリングと通院計画の提示
症状は一人ひとり違うため、状態説明を丁寧に行い、患者様の生活リズムに合わせた通院計画をご提案します。
中には電気治療が苦手を言われる方もご来院されますが、電気刺激を遠赤外線を揺らぎ波動に変えた治療機器もあるため、電気を感じさせない安心できる治療も可能となっています。
⑤ 病院との併用・紹介も可能
必要があれば整形外科・医療機関をご案内し、併用のサポートも行っています。

4.病院と接骨院は併用できる?(よくある疑問)
結論A:併用できます。
病院で診断書や検査
接骨院で専門的なむちうち施術
どちらも自賠責保険適用という形で通院できます。

5.交通事故に関するよくあるQ&A
Q1.むちうちは後から痛みが出るって本当?
A1.本当です。1〜3日後に悪化するケースが多く、早期治療が必要です。
Q2.交通事故の治療費はいくら?
A2.自賠責保険適用で窓口負担0円です。
Q3.転院はできますか?転院の方法なども相談してくれますか?
A3.はい、可能です。保険会社への連絡も当院がサポートします。
Q4.病院に通いながら接骨院にも行けますか?
A4. 併用できます。病院の検査+接骨院のリハビリが最も効果的です。近年併用加療を好ましくないとする病院もありますので、当院に併用加療のご希望がある方は、ご相談ください

6.まとめ|さいたま市緑区で交通事故治療なら専門性のある接骨院へ
交通事故の痛みは時間が経つほど悪化し、後遺症として残りやすくなります。
むちうち・腰痛・肩の痛み・頭痛など少しでも違和感がある場合は、早めにご来院ください。
花月接骨院は、
・交通事故施術の実績
・自賠責保険の知識
・徹底したサポート
・根本改善を重視した施術
がそろった 交通事故に強い接骨院 です。
さいたま市(さいたま市緑区・浦和区・見沼区・南区)の交通事故治療なら、当院に安心してご相談、ご来院ください。

むちうち【交通事故の直後、首が痛くないから大丈夫?むちうちのあとから症状に注意】
交通事故 むちうち 治療?
交通事故の直後、「首は痛くないし大丈夫そう」と思っていても、数日〜1週間ほど経ってから痛みやだるさが出てくることがあります。
これは「むちうち(頸椎捻挫)」と呼ばれる症状の代表的な特徴です。
予期せぬ追突事故の瞬間、身体には強い衝撃が加わります。シートベルトやエアバッグで外傷は防げても、首や背中の筋肉・靭帯は一瞬で大きく引き伸ばされます。
その際に損傷や炎症が起こっても、【交通事故!】に遭遇すると、大多数の方は初めてで、興奮状態に陥るため、すぐには痛みが出ず、交通事故の事故処理が終了して落ち着きを取りも出す頃の時間経過とともに筋肉の緊張や血行不良が進み、「首が回らない」「頭痛がする」「肩が重い」といった症状が現れることが多くみられます。
この時間経過は、事故直後~数時間~数日~数週間とかなりの個人差があります。
むちうちは、症状が軽微な時でも、早めに治療を始めることで、交通事故の治療として首の痛み治療ができ、悪化や後遺症を防ぎやすくなります。放っておくと、天候の変化で痛みが出やすくなったり、慢性的な肩こり・頭痛に発展してしまうこともあります。

交通事故の治療相談や治療はどこにすればいい?
花月接骨院では、事故直後の軽い違和感の治療から保険会社対応、病院紹介までご相談を受付しています。
当院では、交通事故治療に関しての患者様へ流れを説明し、その後、まずは問診と触診で筋肉や関節の状態を丁寧に確認し、痛みの原因に合わせた施術を行います。首を強く動かすような施術はせず、筋肉の緊張を少しずつ緩めて回復を促しますので、初めての方でも安心です。
電気治療が苦手という方には、最新機器の遠赤外線をわずかな共鳴揺らぎ波動治療や
ほとんど電気の流れを感じることのない微弱電気治療など、電気治療が苦手な方にも安心してご来院して頂いてます。
また、整形外科との併用も可能です。レントゲンで骨に異常がないと診断された場合でも、接骨院で筋肉や関節のケアを行うことで、より早い回復が期待できます。
また、自賠責保険が適用されるため、窓口負担は0円で通院できます。
事故後すぐは大丈夫でも、数日後に出てくる痛みが「むちうち」のサインかもしれません。
「少しおかしいな」と感じたら、我慢せず早めにご相談ください。花月接骨院が、痛みを残さないようしっかりとサポートいたします。

病院で湿布だけ出された…そんな時は接骨院でのリハビリが有効?
交通事故のあと、整形外科を受診して「骨には異常ありませんね」と言われ、湿布や痛み止めだけを処方された経験はありませんか?
しかし、痛みや違和感が残っているのに「治療は終わり」と言われると、不安になりますよね。
実は、交通事故による首や腰の痛みの多くは、骨ではなく筋肉や靭帯の損傷によって起こります。
レントゲンでは映らない“見えないダメージ”が原因のため、薬や湿布だけではなかなか改善しないことがあるのです。
そんな時におすすめなのが、接骨院でのリハビリです。
花月接骨院では、事故による身体のバランスの崩れや筋肉の緊張を丁寧に見極め、手技による施術や電気療法で深部の筋肉までアプローチしていきます。
固まった筋肉をやわらげ、血流を促すことで、自然な回復力を引き出します。
また、整形外科との併用通院も可能です。
「病院での診断書をもとに、接骨院でリハビリを受ける」という流れは一般的で、自賠責保険もそのまま利用できます。
医師の診断を受けながら接骨院で施術を続けることで、医療面でも安心してリハビリを進められます。

まとめ
もし「転院したい」「病院との併用はできるの?」といったご不明点があれば、花月接骨院が保険会社との連絡や書類の手続きをしっかりサポートします。
交通事故治療の場合、多くの方は自賠責保険を利用し窓口負担0円で通院できるので、経済的な心配もなくしっかりと治療ができます。
湿布だけでは良くならない首や腰の痛み、だるさ、頭痛…。
「時間がたてば治るだろう」と我慢せず、早めのリハビリで後遺症を防ぐことが大切です。
交通事故後の違和感や痛みが残っている方は、ぜひ花月接骨院にご相談ください。

さいたま市で交通事故治療を受ける時の接骨院の選び方
交通事故に遭ったあと、「どの接骨院に通えばいいのかわからない」と悩む方は多いです。
ケガで接骨院にご通院されたことがある方ならそんなに不安もないかと思いますが、
それでも、痛みを早く取りたい、後遺症を残したくない、交通事故のケガや対応に専門的な接骨院に通院したい。との多くの方のご意見があります。
しかし、
あちらこちらに接骨院があるから、どこに通院良いかわからない。
始めていくところだから不安。
どこに行くのが自分にとってベストだろう?
接骨院でどんな治療をされるのだろう?
そんな方のために、失敗しない接骨院選びのポイントをまとめました。

交通事故の治療!接骨院の選び方!
交通事故治療の多数の症例実績や対応がある院か?
接骨院といっても、すべてが交通事故治療に詳しいわけではありません。
むち打ちや腰の痛み、神経症状などは、事故特有の施術・判断が必要です。
「交通事故専門」「自賠責保険対応」など、HP上には書いてあるけど、本当に経験豊富な院なのか?まずはそこから選択を考えて選ぶと安心です。
花月接骨院(さいたま市緑区原山)では、2000年に開院して以来、これまで数多くの事故患者様を対応しており、早期回復と後遺症防止を重視した治療を行っています。
保険会社や病院との連携が取れているか
事故後は、整形外科での診断書発行や保険会社との書類手続きが必要になります。
この連携がスムーズでないと、治療費の支払いトラブルや打ち切りにつながることもあります。
自賠責保険の流れや書類サポートをしてくれる接骨院を選ぶのがポイントです。
自分の症状に合わせたリハビリが受けられるか
事故による痛み・症状は個人差があります
「痛みが取れた=治った」ではなく、筋肉・関節の柔軟性を取り戻し、再発を防ぐためのリハビリプランが大切です。
当院ではハイボルト治療や手技療法、運動指導を組み合わせ、段階的な治療を行い早期回復をサポートしています。
通いやすさ・相談のしやすさも大事
交通事故治療は数週間~数か月の通院になることもあります。
仕事帰りや学校後でも通える立地、時間帯、駐車場の有無なども大切です。
また、スタッフが親身に話を聞いてくれる環境かどうかも安心材料です。
当院は浦和駅からバス10分(バス停から徒歩1分)、駐車場12台(専用駐車場6台・提携駐車場6台)・自転車置き場もご用意しております。
浦和越谷街道沿いの花月交差点が目印となりますので、近隣の方・車通勤の方も通院しやすい接骨院となります。
また交通事故のケガ等の相談は当院の院長に、交通事故の法律的問題は当院の顧問弁護士にお気軽にご相談できます。

まとめ:迷ったら専門院(本当に交通事故治療に詳しい接骨院)に相談を
交通事故後の痛みや違和感を放置すると、後遺症につながることもあります。
「どこに通えばいいか分からない」と迷ったら、まずは交通事故治療の実績がある専門院へ行きましょう。
花月接骨院(さいたま市緑区原山)では、交通事故による首・肩・腰・膝の痛み、リハビリ、保険手続きまで一貫してサポートしています。
花月接骨院開院25年間(治療実績36年間)の交通事故治療の対応実績があります。
現在も交通事故治療に対しての専門的な研修会に参加中。
遠方で当院にご通院できない方には、当院からお住まい地域の接骨院もご紹介できる場合もあります。
当院にご通院できない時、どこに通院してよいかわからない場合、お気軽にご相談ください

交通事故後のリハビリを途中でやめるとどうなる?再発・後遺症のリスク
交通事故後、痛みが軽くなったからといってリハビリを途中でやめてしまう方が少なくありません。ですが実は、その判断が後遺症の原因になるケースもあります。
今回は「途中でやめるリスク」と「リハビリ継続の大切さ」について解説します。
交通事故のケガの治療をしない・治療を途中で中断してしまうデメリット
症状が残りやすい理由
事故直後は、体の防御反応でアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくくなります。
そのため「痛くない・大したことない・もう治った」と思っても、筋肉や靭帯の損傷が残っていることが多く、しばらく期間が経過したのち(発症や痛みが気に出し始める期間は個人差がかなりあります)特にむち打ち症や腰の痛みは、時間が経ってから再発・慢性化する例が多くみられます。
ケース1
ある患者様は、事故後2週間で痛みが軽くなったためご自身でもう大丈夫!と思い、通院をやめてしまいました。しかし1カ月後、再びやっぱり首の痛みと頭痛が出て再来院。すでに保険会社担当から治療終了の話が来ていたため、残念ながら自賠責保険での治療は不可となってしまいました。
結局自賠責保は使用できず、また健康保険も使用許可が下りなかったため、全額自己負担での治療となってしまいました。
交通事故での衝撃が原因で深部の筋緊張が解消されておらず、今回は早期治療再開したことで少ない治療回数で回復しましたが、放置していれば後遺症になる可能性もありました。

リハビリを続けるメリット
・筋肉・関節の柔軟性を維持し、再発を防止
・血流を改善し、自然治癒力を高める
・神経の圧迫や歪みを整えて、痛みの根本改善につながる
リハビリは「痛みを取る」だけでなく、「痛みを出さない体に戻す」ための重要なステップとなります。

リハビリ治療を途中でやめるデメリット
・しばらくしてからやっぱり痛みがあると思うことがある
・後遺障害がのちに出現する可能性がある
・自賠責を使用しての治療が再開できない

花月接骨院でのサポート
当院(さいたま市緑区原山)では、事故後の症状や回復段階に合わせてハイボルト治療や手技療法、運動リハビリを組み合わせ、早期回復と再発防止をサポートしています。
当院では、
STEP1 急性症状期間・鎮静期
強い痛みの症状・疼痛・可動制限・腫脹・圧痛などの治療期間
多回数の通院を指導します
STEP2 改善期・リハビリ治療期
強い痛みから緩慢的な痛みする頃、残存している疼痛・可動制限、腫脹や圧痛等の治療期間
週2~4回程度の間隔を開けながらの通院を指導します
STEP3 社会復帰期・メンテナンス期
緩慢的な残存する痛み、可動制限、疼痛、圧痛等の治療期間
仕事・日常生活動作・スポーツ・家事作業等に残る支障を改善しながら体のメンテナンス治療を行い、上記の社会復帰後、後遺障害等で悩まないで済むように週1~2回程度の通院を指導します。
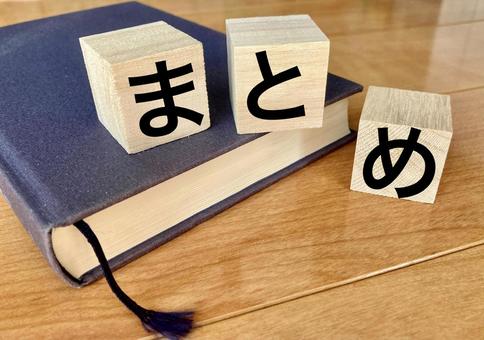
まとめ
交通事故後の痛みや違和感は、軽視しないこと!
他院(整形外科や接骨院)で痛みが残っているのに交通事故治療終了となりそうなとき、「まだ違和感がある」「疲れると痛みが出る」といった方は、保険会社の担当の方と相談しつつ、残された痛みを取るために当院での治療をぜひ一度ご相談を下さい。

接骨院での交通事故治療を受ける時・通院時の注意点
交通事故に遭ったあと、首や肩、腰の痛みが出ても「病院で異常なしと言われたから…」と放置してしまう方が少なくありません。そして、後遺障害に悩んでしまう方も多くいらっしゃいます。
事故後の体の痛みは、時間が経ってから出てくることも多く、病院で異常なしと言われても、ニュアンス的には骨・神経系に異常なしとのことで、筋損傷や関節損傷に細かいところの話まで見ていないケースも多くあります。
上記のようなはっきりしない痛みでも、早期のリハビリや継続的な治療が大切です。
今回は、接骨院での交通事故治療のメリットと通院時の注意点について詳しくご案内します。

接骨院で交通事故治療を受けるメリット
むち打ちなどの筋肉・関節に特化した治療ができる
病院では骨折や外傷に対する検査が中心ですが、接骨院では筋肉や関節、神経に対して手技療法や電気療法などを組み合わせた治療が可能です。
特に首のむち打ち症、腰痛、肩の張りなどは、原因を見極めてアプローチするため、病院で処方される湿布や痛み止めよりも回復が早いケースも多く見られます。
待ち時間が少なく、通いやすい
仕事帰りや学校帰りでも立ち寄れる接骨院が多く、また夕方遅い時間帯まで診療しているところが多いため、病院よりも通院しやすい点がメリットです。
さいたま市緑区原山のような地域密着の花月接骨院も通常受付20時まで、20時以降の来院はTEL予約可能などとしています。また、被害者救済の観点で、交通事故患者様優先予約枠を設けたりしております。特に当院では遠方からも多くの患者様が来られるため、専用駐車場6台・提携駐車場6台、合計12台の駐車場をご用意しています。
駐車場の心配がなく、通りがかりの車通勤の方でも無理なく通院治療ができます。
自賠責保険が使える
交通事故によるケガの場合、自賠責保険で自己負担0円で治療が受けられるケースがほとんどです。
ただし、保険会社や病院との連携が必要になるため、事故後はまず負傷部位の医師診断を受けておくことが大切です。

接骨院に通院時の注意点
医師の診断書を必ず取得する
しっかり自賠責保険の適用させるためには、医師の診断書と定期的な診察が必要です。通院期間や保険会社によっては、接骨院のみの通院では補償を受付けてくれないケースもあるため、整形外科を受診しておくことは間違いありません。
通院を中断しないこと
痛みが残っているのに通院を途中でやめたり、不規則な通院をしていると、治療の効果が不十分になり、保険会社から「治療の必要性なし」と判断されることもあります。痛みの状態に基づいた継続的な通院が大切です。
接骨院と病院の併用が大切
病院で経過を診てもらいながら、接骨院でリハビリを受けることもできますので、医療連携を取り、より安心・効果的な回復を目指し交通事故治療を受けるようにしましょう。

まとめ
交通事故後の痛みは、「骨には異常がない」からといって安心できるものではありません。
筋肉・靭帯の微細な損傷が痛みの原因となることも多く、接骨院での専門的な治療が早期回復のカギになります。
花月接骨院(さいたま市緑区原山)では、交通事故専門治療に対応し、むち打ち症・腰痛・肩の痛みなどの早期改善をサポートしています。
また、交通事故トラブル(過失割合等相談)でお困りの場合、交通事故専門の連携弁護士に無料で相談が可能です。※但し、当院ご通院患者様に限ります
お困りの方はお気軽にご相談ください。