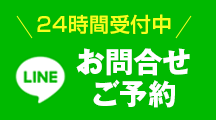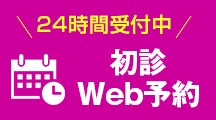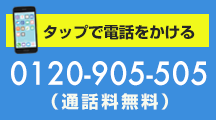Blog記事一覧 > 9月, 2025 | さいたま市緑区の交通事故治療専門院 さいたま市緑区交通事故治療情報センターの記事一覧

自転車と歩行者の非接触事故とは?接触がなくても事故になるケース
非接触の交通事故というと、車同士・車と歩行者・車とバイクが「ぶつかりそうになった瞬間」をイメージしがちですが、自転車と歩行者でも、接触がなくても事故として扱われるケース=非接触事故 があります。
自転車と歩行者の間でも起こり得るトラブルで、特に都市部や住宅街では年々増加傾向にあります。
これもレンタルシェアの電動キックボード・電動自転車も大きく影響しています

自転車と歩行者の非接触事故の具体例
事例1
歩行者を避けようとして単独転倒
自転車が歩行者を避けて急ハンドルを切り、縁石や壁に衝突。歩行者に触れていないのに事故とされるケース。
事例2
歩行者が驚いて転倒
自転車がスピードを落とさずすれ違い、歩行者が驚いて転びケガをした場合。接触していなくても「事故」と判断されます。
事例3
狭い歩道でのすれ違い
自転車が近くを通過した際、歩行者がバランスを崩して転倒。高齢者や子どもに多いケースです。

けがをした場合の法律・責任の考え方
自転車は法律上「軽車両」であり、車両としての注意義務が課されています。
非接触でも、歩行者の転倒やケガとの因果関係が認められれば、自転車側に賠償責任が発生します。
実際に裁判例でも「自転車の通行態様が危険だった」と判断され、自転車側に賠償が命じられたケースがあります。
実際にあった事例
当院に通院されたケースでは、歩道を走行中の自転車が高齢者のすぐ横を通過。接触はなかったものの、高齢者が驚いて転倒し、手首を骨折しました。自転車側は「ぶつかっていない」と主張しましたが、周囲の目撃証言や状況から「非接触事故」と認められ、治療費や慰謝料が支払われました。
子どもと自転車の事故事例 【日常で起こりやすい接触事故・非接触事故の危険と対策】
近年、通学や遊びで自転車を利用する子どもの事故が増加中。
自転車は便利な移動手段ですが、交通ルールを十分理解していない子どもが走行することで、思わぬ事故につながることも少なくありません。
1.飛び出し事故
子どもが路地や駐車場から急に飛び出し、自動車やバイクと衝突。特に見通しの悪い交差点で多発。
2.一時停止無視による事故
通学路や歩道から車道に出る際、一時停止を守らず車と接触(非接触)するケース。
3.二人乗りや悪ふざけ運転
友達と悪ふざけながら走行し、バランスを崩して転倒。たまたま歩いていた歩行者や他の自転車を巻き込むこともあります。
4.夜間・無灯火での事故
反射材やライトを使わず走行し交通事故につながるケース。

保護者が知っておきたい!万が一子供が自転車事故を起こした時の対策ポイント
子どもの自転車事故は【加害者】【被害者】の両方になるリスクがあります。
歩行者に接触・非接触でも転倒させた場合には、損害賠償責任を負うことがあります。
実際に、小学生が歩行者と接触しケガをさせてしまい、保護者に数千万円規模の賠償命令が出た裁判例もあります。
万が一の対策は、自転車保険の加入義務化が全国で進んでいるため、万一に備えた保険加入が必須の対策となります。
まず自転車に乗せる前に保護者としての予防対策を行ってから自転車に乗せましょう。そして、子供が自転車事故を起こさないように、親として教えていきましょう。

電動自転車・電動キックボードの事故例 【便利さの裏に潜むリスク】
電動アシスト自転車は、子育て世代や高齢者を中心に利用が増えています。坂道もラクに走れる便利な乗り物ですが、その反面、重量の重さやスピード感が原因で重大事故につながるケースも増えています。
電動自転車の主な事故例
1.子どもを乗せての転倒事故
前後にチャイルドシートを装備したタイプは重心が高く不安定。停車中や発進時にバランスを崩し、子どもごと転倒してケガをするケース。
2.ブレーキの効きすぎ・操作ミス
坂道でアシストが効いたままスピードが出て、急ブレーキで転倒。特に高齢者に多い事故です。非接触事故にもつながります
3.駐車時の倒れ込み事故
車体が重いため、スタンドがしっかり固定されずに倒れ、周囲の人にケガをさせてしまうことも。これも接触事故・非接触事故につながります
4.歩行者との接触・非接触事故
普通の自転車よりもスピードが出やすく、歩行者が驚いて転倒するケース。接触していなくても「非接触事故」として責任を問われる場合があります。
電動自転車・電動キックボードの利用について
便利さの反面、普通の自転車以上に注意が必要!
普通の自転車よりもスピードが出やすく、歩行者が驚いて転倒するケース。接触していなくても「非接触事故」として責任を問われる場合があります。
電動自転車も「軽車両」扱い、事故を起こせば賠償責任が発生します。
子どもや歩行者にケガをさせた場合、多額の損害賠償となる例もあります。
万一に備えた保険加入が必須です。

自転車との非接触の交通事故に遭ったときの対応
1.警察に通報する。「事故証明」を必ず取る
2.連絡先交換・自転車保険や傷害保険を確認
3.目撃者がいれば証言を確保
4.自覚症状がなくても医療機関・接骨院を早めに受診
(後からむち打ちや腰痛、打撲痛が出るケースもあり)

花月接骨院でのサポートとまとめ
非接触事故でも自賠責保険や任意保険が適用される場合があります。
当院では、事故直後の応急処置からリハビリ・保険の対応相談までトータルでサポートしています。さいたま市緑区原山の花月接骨院【0120-905-505】までお気軽にご相談ください。
自転車との接触事故・非接触事故では、警察に連絡する(事故証明が取れること)が、重要です!

自動車同士の非接触事故とは?接触していなくても事故になるケース
一般的に「交通事故=車同士の衝突」のイメージを持つ方が多いですが、実際には車がぶつかっていなくても交通事故と認定されるケース=【非接触事故】も存在します。
これは法律上も「交通事故」と認められる場合があり、加害者・被害者双方にとって非常に判断が難しい事故のひとつです。
法律上は「他の車の運転行為によって事故が発生した」と認められれば交通事故とされ、自賠責保険や任意保険の補償対象になります。

非接触事故の具体例
進路妨害による回避行動
交差点で急に割り込んできた車を避けようとして縁石や電柱に衝突したり、対向車や横から割り込んできた車を避けるためにハンドルを切り、ガードレールや電柱に衝突してしまった場合。
→ 実際に接触はしていませんが、進路妨害が原因で事故が発生しています。
加害車両とは接触していなくても、その危険な行為が原因と認められる可能性があります。
急な割り込みや急停止、急な進路変更
前の車が急に割り込んできてブレーキを踏んだ結果、後続車が単独でスリップ・転倒してしまうケース。
→前を走る車が合図なしに急停止し、後続車がスリップして単独事故。この場合、前方車の過失が発生するケースとなります。
二輪車との関係(幅寄せによる二輪車の転倒)
車がバイクや自転車を無理に追い越そうとして幅寄せ、接触はしてないがバランスを崩して転倒。
→このケースは実際に多く、ドライブレコーダー映像が決め手になることが多いです。
路上障害物を避けるように追い込まれたケース(進路妨害)
大型車が進路をふさぐように走行し、避けた結果ガードレールに接触。

過失割合の考え方
非接触事故では、加害車両が存在することをどう証明するか が大きなポイントになります。
加害車両が特定できる場合
→ 危険な運転が証明されれば、加害車側の過失が大きくなります。
加害車が明確に特定され、危険な運転が立証できれば「加害車側の過失」が大きく認められます。
加害車両が特定できない場合
→ 単独事故とされることが多く、被害者自身の保険(人身傷害補償など)を使うことになります。
加害車がそのまま走り去ってしまい、証拠がない場合は「単独事故」とされてしまうケースも少なくありません。また、証拠が乏しい場合、保険会社とのやり取りが難航するケースがあり、早めの専門相談が必要です。
このため、ドライブレコーダーの映像や目撃証言の確保が極めて重要となります。

実際にあった事例
事例1
当院に通院された患者様のケースでは、交差点で横から割り込んできた車を避けてハンドルを切ったところ、縁石に乗り上げて事故になりました。相手車両は止まらずに走り去りましたが、幸いドライブレコーダーに映像が残っており、保険会社に「非接触事故」として認められ、治療費も自賠責保険で補償された事例があります。
事例2
当院に来院された患者様のケースでは、交差点で右折してきた車がセンターラインを大きくはみ出し、避けようとしたところ縁石に衝突。相手の車は接触せずにそのまま走り去りました。幸いドライブレコーダーに映像が残っており、警察も加害車の特定に動いてくれたため、自賠責保険を利用して治療が可能になった事例があります。
事例3
当院に通院された患者様のケースでは、交差点を直進進入した時に、対向車がいきなり右折を開始してきたため、急ブレーキをかけ何とか急停車出来たが、車内の荷物は散乱破壊、同乗者はシートベルト損傷や強いムチウチ負傷となりました。
相手車両が逃走しようとしたところ、同乗者が車両及び車のナンバーを警察に連絡できたため、加害者車両を捕獲し、またドライブレコーダーにて、【相手の過失を証明の立証】ができたため、自賠責保険及び任意保険を利用し治療可能になった事例があります。

非接触事故に遭ったときの対応
1.すぐに 警察へ通報する。
【加害車両の特徴・ナンバー・逃走方向】
2.ドライブレコーダー映像や目撃証言を確保する。警察に相手車両を特定してもらう。
3.保険会社に「非接触事故であること」をしっかり説明
4.自覚症状が軽くても必ず早めの段階で、医療機関や接骨院を受診する(後からむち打ちや腰痛が出ることが多い)

花月接骨院でのサポート
非接触事故の場合でも、むち打ち症・腰痛・打撲などの症状が出ることは珍しくありません。自賠責保険・任意保険での治療が可能となります。
もちろんこちら側に過失が大きくある場合は、健康保険扱いになる可能性もあります。
当院では、事故直後の検査・施術・医療機関紹介、保険会社とのやり取りに関するご相談は顧問弁護士に無料相談できるようにサポートしています。
非接触事故でお困りの場合、【さいたま市緑区原山の花月接骨院0120-905-505】まで早めの段階でご連絡ください。

まとめ
非接触事故は「証明の有無」がすべて。ドライブレコーダーの装着は非常に有効です。
またドライブレコーダーがなかった場合、事故現場の防犯カメラ映像の保存できるようでしたら、早めに対応するようにしてください。
交通事故過失割合シリーズの総まとめ
結論:過失割合紛争トラブルに巻き込まれないようにするために!
最重要はドライブレコーダーを装着すること!そして必ず事故の映像を保存すること。
別冊判例タイムズ38号による過失割合だけで判断されないようにしましょう!

高速道路での交通事故と過失割合について
高速道路は一般道路と比べて速度が高く、事故が起こると被害が大きくなりやすい場所です。特に追突事故や車線変更時の接触事故は頻繁に発生します。今回は、高速道路でよくある事故パターンと過失割合の考え方、実際の対応のポイントについて解説します。

よくある高速道路上の交通事故パターン
・追突事故(渋滞中や減速時)
高速道路では急な渋滞や減速が原因で追突が多発する交通事故。
過失割合は「追突車:前方車=100:0」が基本。
・車線変更時の接触事故
無理な車線変更や死角確認不足による交通事故。
基本的には「車線変更車の過失が大きい」です。
しかし相手車両が、極端にスピードを出していた場合は過失割合修正されることもあります。
・合流地点での事故
高速道路への合流や分岐での接触。
「合流車の過失が大きい」とされます。
しかし本線走行車両側にも注意義務があるため、場合によっては7:3や6:4になってしまうこともあります。

実際にあった高速道路の交通事故のケガ事例
高速道路の渋滞末尾で停車中に後方から追突され、さらにその後続車が玉突きのようにぶつかってきたケースがありました。首のむち打ち症状が長く続き、日常生活や仕事にも影響が出ました。このように高速道路での事故は衝撃が強く、後遺障害に発展するリスクも高いケガとなることが特徴のひとつです。

高速道路事故に遭った時の対応
・すぐに路肩や安全な場所へ避難する(二次事故防止が最優先)
・ハザードランプ・発煙筒・三角表示板を使用
・110番通報・NEXCOへ連絡
・けがをした場合は速やかに救急搬送を依頼し、その後は病院で精密検査を受けてください。

花月接骨院でできるサポート
高速道路の追突事故・玉突き事故・多重事故では体が受ける衝撃が強く「むち打ち症」や「腰の痛み」の治療が長期になるケースがあります。
花月接骨院は、スポーツ障害・スポーツのケガの治療の早期快復ができる接骨院です。交通事故の強い衝撃性(炎症期からリハビリ期)までその急性期・亜急性期・慢世紀の症状に合わせた合わせた施術を行い、できる限り日常生活に支障をきたさないように早期回復の治療を行います。
高速道路での交通事故のケガの場合、遠方での救急病院受診が多くなる傾向で、地元に戻ってきてからの病院転院・リハビリ等のご相談が多くあります。
当院では、セカンドオピニオンができる病院をご紹介し、医療連携で交通事故治療も可能です。
ご相談は 0120-905-505さいたま市緑区原山の花月接骨院までお気軽にどうぞ。

追突による玉突き事故の過失割合と対応
交通量の多い道路や渋滞時に特に起こりやすいのが「追突による玉突き事故」です。
前方の車が急停止した際に、後続車が追突し、その衝撃でさらに前の車へと次々にぶつかってしまう交通事故のケースです。
一度に複数台が関わるため、当事者間で「誰が悪いのか」「修理費用はどこに請求するのか」といったトラブルに発展しやすい交通事故のひとつです。

玉突き事故の過失割合
玉突き事故では、基本的に後方から追突した車両に過失が大きくなるのが原則です。
ただし、事故の状況によって過失割合は変わります。
前方車が急ブレーキをかけた場合
通常は後続車に前方不注意があると判断されますが、急ブレーキが不自然な場合(進路妨害や危険運転など)には前方車にも一部過失がつくことがあります。
渋滞中の玉突き
信号待ちや渋滞停止中に、後ろの車が突っ込んできた場合は、基本的に最後尾の車の責任が大きくなります。
※ただし「二番目の車が適切な車間距離を保っていなかった」場合は、その車にも一定の過失が発生することがあります。
高速道路での多重衝突
霧・雪・雨などの悪天候や視界不良で発生するケースでは、複数台に責任が及ぶこともあります。状況証拠や実況見分の結果によって過失割合が大きく変動します。

実際にあったケース
信号待ちで停車中に後方からトラックに追突され、その衝撃で前の車にもぶつかってしまいました。ご本人は「自分が前の車にぶつけてしまったから責任があるのでは」と不安に感じていましたが、実際には原因となった最後尾のトラックに過失となりました。
このケースでは、自賠責保険と任意保険を併用して治療費・修理費がカバーされ、通院治療もスムーズに進みました。

玉突き事故に遭った時の対応ポイント
・事故直後は 安全確保と二次被害防止 を最優先
・すぐに警察へ連絡し、必ず事故証明を取得
・関わった車の運転者・同乗者の連絡先を控えておく
・自分が「前の車に当たったから過失がある」と早合点せず、保険会社・弁護士に相談
・首や腰のむち打ち症は、後から症状が出ることが多いため、必ず医療機関や接骨院で診察を受ける

花月接骨院でのサポート
玉突き事故では、第一次の後方からの衝撃と第二次の前方衝突による衝撃が強く、
首・肩・腰・シートベルト装着部にダメージが残りやすいのが特徴です。
むち打ち症、腰痛、頭痛、手足のしびれ、シートベルトによる胸部打撲・肩部打撲など、後から出てくる症状も少なくありません。
花月接骨院(埼玉県さいたま市緑区原山)では、玉突き事故のケガの場合でも、しっかり自賠責保険を使った交通事故治療に対応し、交通事故治療のサポートと顧問弁護士による無料相談を行っておりますので、お困りの際は 【花月接骨院(0120-905-505)】 までお気軽にご連絡ください。患者様の身体の早期快復をサポートいたします。

交差点での車とバイク事故と交通事故過失割合
交差点は車同士だけでなく、バイクとの接触事故も多発する危険な場所です。バイクは小回りが利き視認性も低いため、四輪車から見落とされやすいという特徴があります。
・特にバイクは車体が小さく見落とされやすいこと(死角に入りやすい)
・転倒のリスクが高いこと(二輪であること)
・左折車に巻き込まれやすいこと
・車との速度感覚が異なること
など、交差点でのバイク事故は守る車体が無いこともあり、重大なケガにつながりやすい特徴があります。
交差点でのバイク事故は、過失割合の判断が難しいケースが多いです。
今回は「交差点で起こるバイク事故」に焦点を当て、過失割合や注意点について解説していきたいと思います。

交差点でのバイク事故の代表的なケース
右折車と直進バイクの衝突
車が右折しようとした際に、直進してきたバイクと衝突するケース
→ この場合、原則的には直進優先のため、車側の過失が大きくなります。
過失割合例:車80%:バイク20%
※ただし、バイクが著しくスピードを出していた場合や、信号無視をしていた場合はバイク側の過失も加算されます。
信号無視による衝突
信号を無視した車やバイクが交差点に進入し、衝突するケース
→信号無視をした側の過失が大きくなります。
過失割合例:信号無視した側90%:被害側10%
出会い頭の事故
信号のない交差点で、優先道路側を走るバイクと、非優先道路から出てきた車の衝突したケース
→ 優先道路を走行していたバイクに有利に働くことが多く、車側の過失割合が大きくなります。
過失割合例:車90%:バイク10%
左折車と直進バイクの接触
車が左折する際に並走していたバイクと接触するケース。
四輪車が巻き込み確認を怠った場合、車側の過失が大きくなります。
過失割合例:車70~80%:バイク30~20%

バイク事故の特徴
・車と違い、ちょっとした衝突でも転倒しやすいため ケガの重症化リスクが高い。
・相手が「バイクはスピードを出している」と主張し、過失割合の交渉でトラブルになりやすい。

バイク運転者の交通事故対策
バイク用のドライブレコーダーを装着しておくこと
バイク事故の場合、大きなけがのリスクが高くそのまま救急搬送されてしまうことが多い為、その後の事故現場検証には、ドライブレコーダーがとても重要になります。
ない場合は事故現場付近の防犯カメラも主張に役に立つこともあります。
自分の主張を立証するためにもドライブレコーダーは装着しておきましょう!
・バイクは常に「見落とされやすい存在」であると意識する
・交差点では減速し、ドライバーの動きをよく観察する
・夜間はライトや反射材を活用し、視認性を高める
実際にあったケースからのアドバイス
青信号で直進していた際、右折車に巻き込まれる形で正面衝突し、転倒し大きなケガを負いました。
相手側は「バイクがスピードを出していた」と主張
しかし交差点付近の防犯カメラ映像があったためその映像が証拠となり、最終的には 車の過失が80%以上 と認定されました。
バイク事故では 証拠の確保が命綱。可能であればドラレコをつけておく、事故後は周囲のカメラ位置を確認するなど、早めの行動が大切です。

まとめ
交差点でのバイク事故は、車のドライバーから見落とされやすく、被害者側が大きなダメージを受けやすい事故となります。
交差点でのバイク事故は「車が大きな過失を負うケース」が多いですが、バイクの速度超過や無理なすり抜けが認定されると過失割合が変わる交通事故となります。
車の運転者は、
・直進バイク優先の原則を覚えておく
・信号や優先道路の有無で過失割合が変わる
・事故後は証拠をしっかり確保する
・左折・右折時に必ず後方・死角を確認する
バイクの運転者は、
・ドライバーは自分が見えていないと思いながら運転すること
・交差点では左折車の巻き込み事故のリスクがある危機感を持つこと
・交差点直進するときは、対向車が急に右折してくるリスクがある危機感を持つこと
・高速道路では、渋滞時にすり抜けをしないようにすること
これらを意識するだけでも、バイク運転中による交通事故のリスクに大きな違いが出てきます。
もしバイクで交通事故に遭われてしまった場合は、治療だけでなく過失割合や保険対応で悩むことも多いです。
当院では、交通事故治療のサポートと顧問弁護士による無料相談を行っておりますので、お困りの際は 【花月接骨院(0120-905-505)】 までお気軽にご連絡ください。